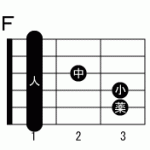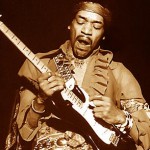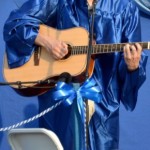耳コピのやり方は、根気いる作業です。
譜面を見たことがないのに、カラオケで歌を歌えるのなら、耳コピは出来てます。
では、ギターで耳コピをするには…。
耳コピは絶対音感がなくても出来ます
私の親の世代は、今のように楽譜などほとんど売ってなく、レコードが擦り切れるほど何度も聞いて、「耳コピをしていた」と、言ってました。
クラッシックから音楽を始めた人は、譜面を読むところから始めるので、耳コピが得意でないことが多いです。
独学で始めたギターリストの方が、譜面が読めないからと、耳コピが上手な時があります。
販売されているバンドスコアには結構、音の間違えがあります。
採譜と言って、耳コピして楽譜に書き起こしている人がいます。
採譜職人が、全部の楽器を理解しているわけではないので、ありえない運指のギタータブ譜など、よくあります。
どういう指をしたら、届くんだろうと必死に考えたら、となりの弦に同じ音があったということがあります。
ライブ映像やPVを見て、「どこのポジションで弾いているか?」など、研究しているギターリストは多いです。
音もリズムも間違っていることがあるので、好きなバンドの曲を弾くときは耳コピは出来た方がいいです。
効率の良い耳コピのやり方
再生速度を落とせる機材を使います。
パソコンのソフトでもありますし、スマホのアプリでも曲の再生の速度をいじれるものはあります。
再生速度を落としつつ、まず、リズムパターンを把握してください。
1小節分のリズムの譜割りを、コピーします。
単音の耳コピならば、1オクターブは12音なので、12回試せばどれか当たります。
リズムと音を同時に拾おうとするから難しくなり時間がかかります。
分けて考えたら、結構簡単です。
問題は和音です。とりあえず拾える音だけ拾っておきます。
始めは、動きのある特徴的な音や、聞き取れる音だけで構いません。
何度聞いても聞き取れない音は、演奏する時に初めて聞くような他人が聞いても違和感すら感じないことが多いです。
さらに一歩進めるには、拾った音からその曲のKeyを割り出します。
Keyがわかれば使えるコードもわかります。
曲調によって、テンションを含めたよく使うコードは慣れればわかってくるので、アナライズの数をこなす必要があります。根気良く続けましょう。
音楽理論がわかってくると、4和音以上のコードネームは作った本人しか分からないことがあります。
ベースの音をオンコードと捉えるのか、上で鳴っている音をテンションと捉えるのかわからなくなる時があります。
その時は、演奏する本人が読みやすいコードネームで大丈夫です。
ゆっくりと丁寧に行ってください。
さらに知識が深まる人気記事
ピアノ関連
>>>ピアノのコードの押え方と考え方<<<
ボーカル関連
>>>歌が上手くなる方法<<<
ギター関連
>>>ギターの弦がびびる原因とは?<<<
リズム関連
>>>5連符&2拍3連の数え方<<<
音楽理論関連
>>>作詞作曲のコツ<<<
ライブ関連
>>>衣装の決め方<<<
雑学関連
>>>肩こり予防の体操<<<